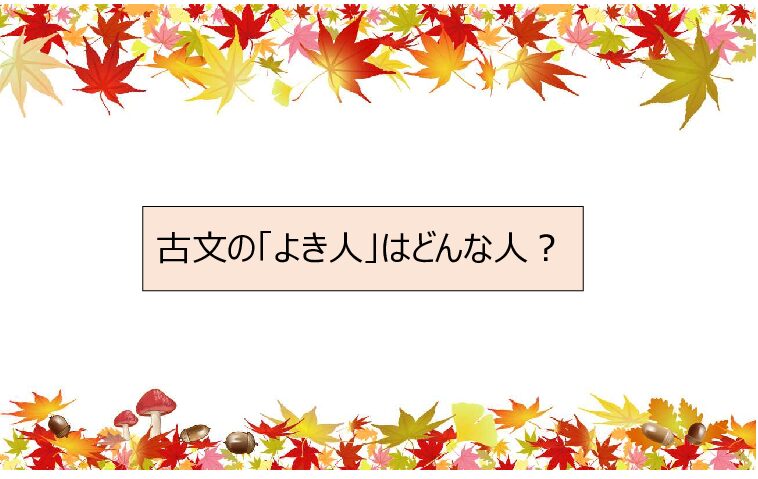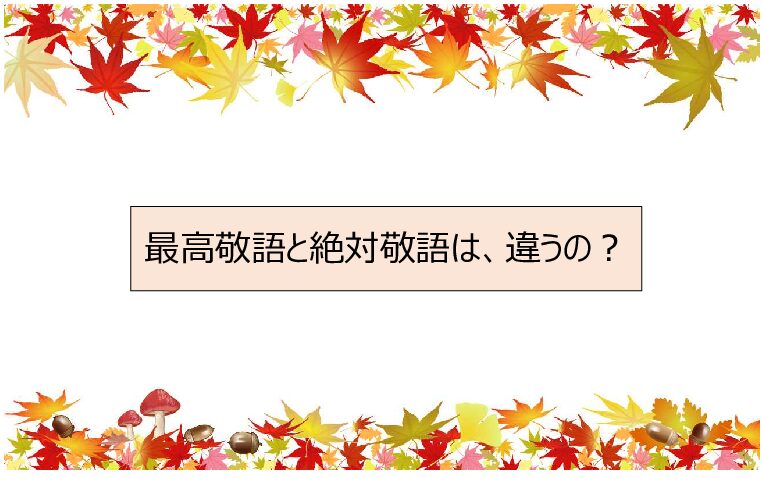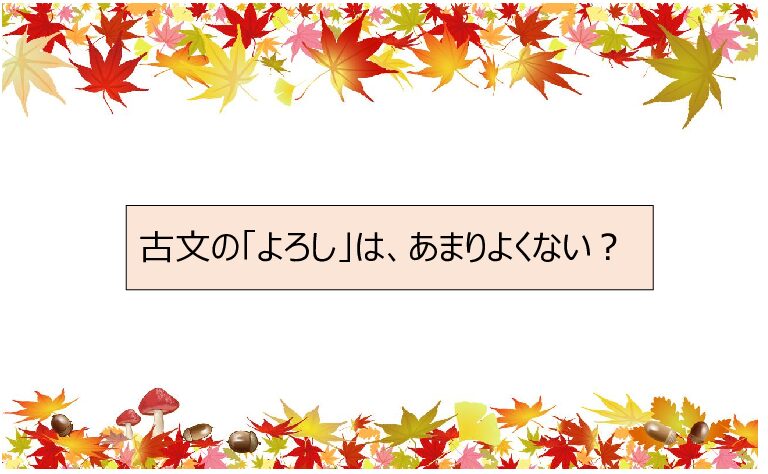古文の文章に時々出てくるものの、意味を調べようとして辞書を引いても、項目が立てられておらず、困ってしまう言葉のひとつに、「よき人」があります。
辞書では直接調べられませんが、言葉自体としては重要なものであり、的確な理解が必要です。
この記事では、そんな「よき人」について説明します。
1 古文の「よき人」は、現代の「いい人」とは違う
古文の「よき人」は、形容詞「よし」の連体形と名詞「人」からできた連語です。
対応する言葉を、現代語で探せば、「いい人」がそれに当たります。(「よき人」を、そのまま現代語に置き換えると「よい人」となりますが、現代語では普通、「よい人」ではなく「いい人」といいます。)
そのような、現代の「いい人」は、主に、〈性格や人柄のよさ〉を持つ人の意で使われます。
現代の「いい人」 性格や人柄のよい人・善良な人
といった意味です。
これに対して、古文の「よき人」は、〈性格や人柄のよさ〉ではなく、〈身分や生まれのよさ〉を持つ人、さらにはそのような人が兼ね備えていることの多い、〈深い教養〉を持つ人、などについて使います。
古文の「よき人」 身分の高い人・教養のある人
この記事の冒頭で、「よき人」は、古語辞典で調べられないといいましたが、実は、形容詞「よし」を引くと、その中の例文に「よき人」が出てくる場合があります。
例えば、『旺文社全訳古語辞典 第五版』では、形容詞「よし」の説明のうち、
④身分が高い。教養があり、上品である。
の項目の例文に、
(例)よき人の、のどやかに住みなしたる所は、さし入りたる月の色も、ひときはしみじみと見ゆるぞかし(徒然草・10段)
(訳)教養のあるりっぱな人が、ゆったりと住み暮らしている家は、さし込んでいる月の光も、一段としんみりと感じられるものであるよ。
というのが載せられています。
ここでは、「よき人」が「教養のあるりっぱな人」と訳されています。
2 古文の「よき人」~『枕草子』の場合
古文の「よき人」の、おおよその意味を理解したところで、それを実際の例文で確認してみましょう。
まずは、『枕草子』の例です。
(例)よき人さらなり。えせ者、下衆の際だに、なほゆかし。(枕草子・とくゆかしきもの)
(訳)身分の高い人は言うまでもない。つまらない者、低い身分の者でさえ、やはり知りたい。
これは、「とくゆかしきもの(=早く知りたいもの)」の段の一節で、誰かが子を産んだときに、その子の性別を知りたい、という記述の一部です。
「よき人はさらなり」は、「よき人」の子である場合は、「さらなり(=言うまでもない)」の意で、言葉を補って訳せば、「身分の高い人の場合は言うまでもなく、早く知りたい」となります。
それに続く、「えせ者・下衆の際」は、「つまらない者・低い身分の者」の意を表し、「なほゆかし」は、「やはり知りたい」の意です。
ここでは、「よき人」と「えせ者・下衆の際」が対比されていて、「よき人」が、「身分の高い人」を指していることがよく分かります。
このほか、「文言葉なめき人こそいとにくけれ(=手紙の言葉が無礼な人はひどく憎らしい)」の段で、「よき人」と「田舎びたる者(=田舎じみた者)」を対比して使う例などがあります。
この場合の「よき人」は、「田舎びたる者」と対照的な人物、つまり、そのまま置き換えると、「都の人」といった意味になりますが、それは、単に「都に住んでいる人」というよりも、「(都の人らしく)教養のある人」、あるいは、「(都ふうに)洗練された人」といった意味で捉えるとよいでしょう。
3 古文の「よき人」~『徒然草』の場合
次に、『徒然草』の例を見ましょう。
(例)下ざまの人の物語は、耳驚くことのみあり。よき人は怪しきことを語らず。(徒然草・73段)
(訳)身分が低い人の話は、聞いて驚くことばかりがある。身分が高い人はおかしなことを語らない。
この段は、人々が面白がって話を盛ったり、嘘をついたりするという行為について書かれています。
引用箇所では、「下ざまの人」と「よき人」とが対比されています。
「下ざまの人」とは、「身分が低い(ほうの)人」の意で、その「下ざまの人」と対比される「よき人」は、「身分が高い人」の意となります。
このほか『徒然草』にも、「よき人」と〈田舎の人〉とが対照的に記述されている箇所があります。
例えば、79段では、「よき人」と「片田舎よりさし出でたる人(=片田舎から出てきた人)」とが対比され、137段では、「よき人」と「片田舎の人」とが対比されています。
これらの例を通してみると、『徒然草』の「よき人」も、『枕草子』と同じく、「身分が高い人」のほか、「(都の人らしく)教養のある人」、あるいは、「(都ふうに)洗練された人」の意味を持っていることが分かります。
4 まとめ
それでは記事をまとめます。
①身分の高い人・(都の人らしく)教養のある人・(都ふうに)洗練された人の意を表す。