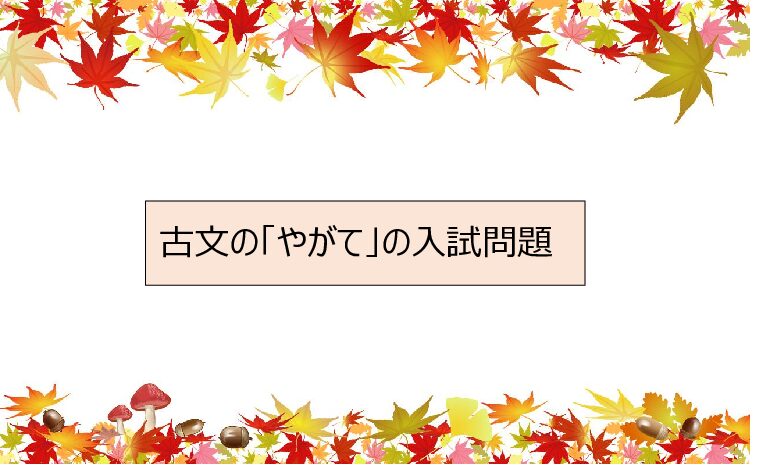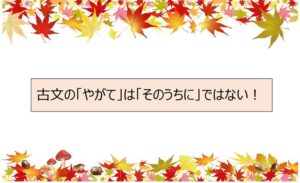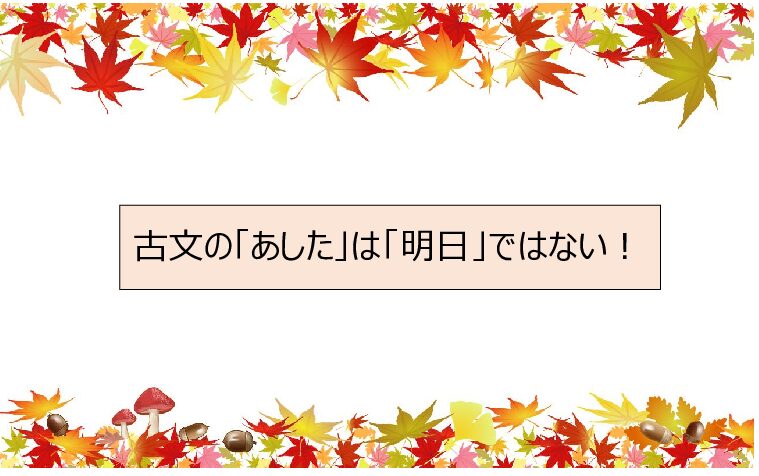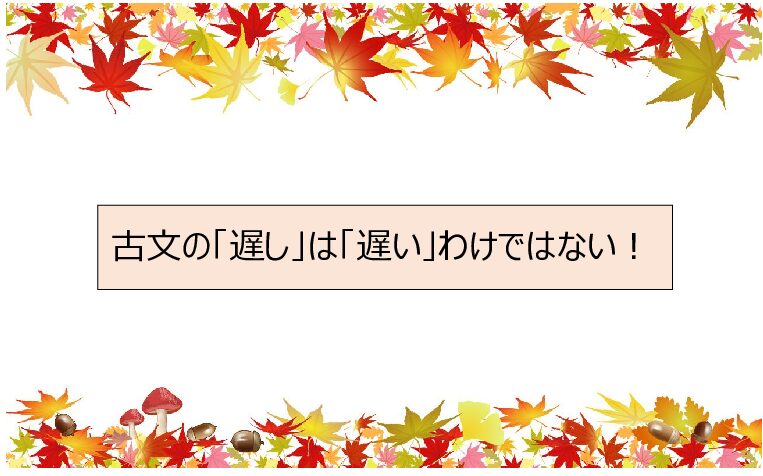以前の記事で、古語の「やがて」の意味についてまとめました。
結論部分を確認すると、
①「やがて」の前後が異なる動作・状態 →すぐに
②「やがて」の前後が類似の状態 →そのまま
でした。
この知識をもとに、実際の入試問題を解いてみましょう。
1 設問
少し古い問題ですが、1997年度のセンター試験・本試験の問1の(ウ)です。
出典は、鎌倉時代の『松浦宮物語』です。
(本文)……去年より、松浦の山に宮をつくりて、……「……たれもむなしくあひみぬ身とならば、やがてその浦に身をとどめて、……」(1997年度 センター試験・本試験)
① まもなく
② いつかは
(ウ) やがて ③ そのうち
④ そのまま
⑤ すぐさま
本文は、必要な箇所のみを抜粋しました。
答えを選んでから、続きをお読みください。
2 簡単な解き方と答え
この設問は、「やがて」の意味を直接尋ねる問題です。
解き方の基本は、「やがて」の前後にある動作・状態を比べて、それらが異なるものか、同じ(類似の)ものかを考えて決める、という方法ですが、この設問は、選択肢を見るだけでも正解が分かります。
選択肢のうち、「やがて」の意味を満たす正解の候補は、
①まもなく ④そのまま ⑤すぐさま
の3つです。
ちなみに、③「そのうち」は、現代語の「やがて」の意味に合わせた誤答です。うっかり、引っかからないように注意しましょう。
さて、本題にもどって、先の正解の候補3つは、意味の上から、
①まもなく ⑤すぐさま ←→ ④そのまま
と分けられますが、実はこの時点で、正解が④であると判断できます。
なぜなら、①の「まもなく」と⑤の「すぐさま」は、言葉の意味が近いため、①「まもなく」が正解で、⑤「すぐさま」が不正解であるとか、反対に、①「まもなく」が不正解で、⑤「すぐさま」が正解であるといった可能性はほぼありません。
もし、そのようなことがあれば、出題ミスとして問題になるでしょう。
そのため、①の「まもなく」と⑤の「すぐさま」は、どちらも正解の候補から外れ、残った④の「そのまま」が正解となるのです。
以上は、ややテクニカルな解き方のため、正攻法を利用した解法も行ってみます。
3 正攻法の解き方
正攻法で必要なのは、「やがて」の前後の動作・状態の確認です。
本文は、遣唐副使(=遣唐使の一員で、大使の補佐を行う)に選ばれた少将が、唐に向かうことになり、両親と別れる場面です。
少将の母親は、息子を案じて、都よりも唐に近い松浦の山(肥前国)に御殿を建て、そこで息子の帰りを待とうと考えました。
本文は、その事柄を受けて、
たれもむなしくあひみぬ身とならば、やがてその浦に身をとどめて、
と続きます。
「たれもむなしくあひみぬ身とならば」は、〈少将が戻ってこられず、(自分を含めた)誰もが再会のできない身となるならば〉の意です。
そして、そうなった場合、少将の母は、「やがてその浦に身をとどめて……」と言っています。
その浦は、松浦の山近くの海辺を指しています。
したがって、「やがて」の前後の状態を整理すると、
〈松浦の山で待つ〉 やがて 〈松浦の海辺に身をとどめる〉
という関係になります。
厳密に言えば、「松浦の山」と「その海辺」は別の土地ですが、いずれも肥前国・松浦郡にあり、「やがて」の前後は、どちらもほぼ同じ場所にいる状態と判断できます。
よって、この「やがて」は、「そのまま」の意と見るのが適切です。
4 まとめ
「やがて」の意味は、④「そのまま」
最後に、該当箇所の訳を載せておきます。
(訳)去年から、松浦の山に御殿を造って、……「……誰も空しく(あなたと)会うことのない身となるならば、(都へは帰らず)そのままその海辺に身をとどめて、……」