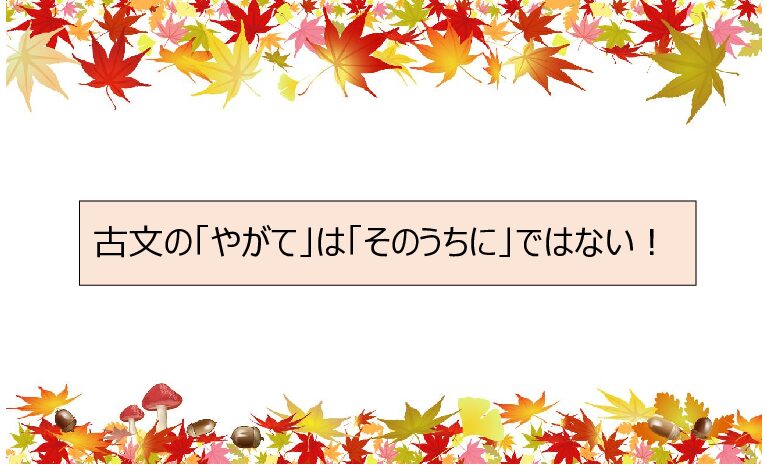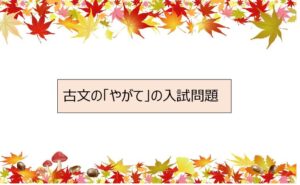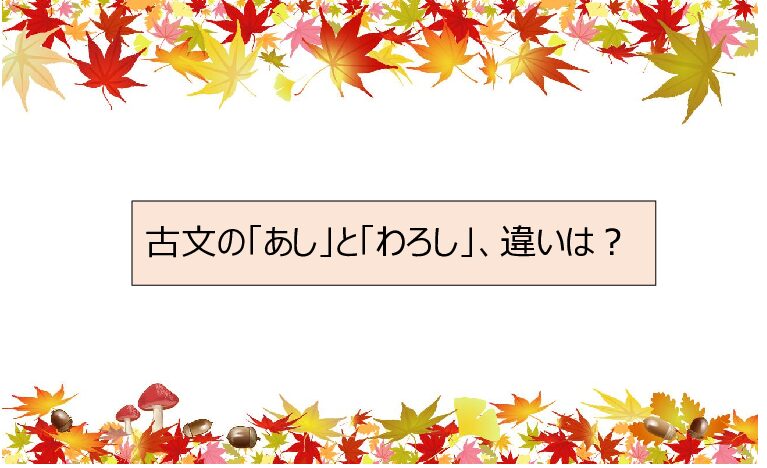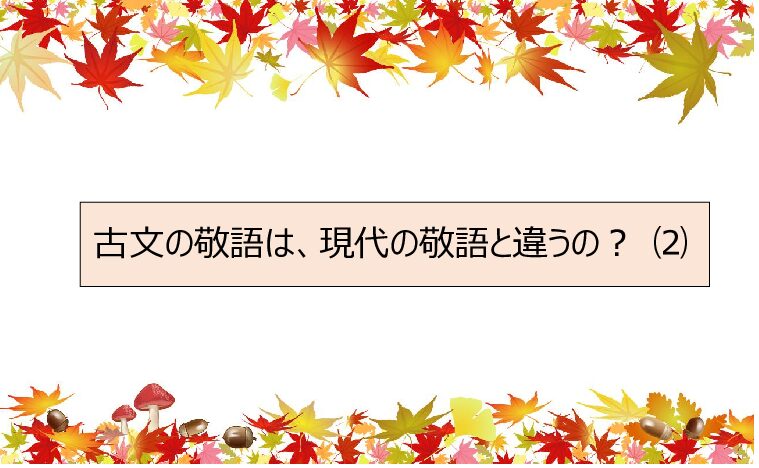古文を読む際に注意が必要な言葉のひとつは、現代語と古語で意味の違う言葉です。
現代語にもある言葉だと、つい、現代語と同じ意味だと思ってしまい、それで文脈を取り違えてしまうことがあるからです。
今回紹介するのは、そのような言葉の中の「やがて」という副詞です。
「やがて」は、古語にも現代語にもありますが、古語の方が意味の範囲が狭く、限定されています。
そのため、現代語と同じつもりで考えると、古語の意味の範囲を越えてしまうのです。
以下、具体的に見てゆきましょう。
1 現代語の「やがて」
現代語の「やがて」は、主に次のような意味で使われます。
現代語の「やがて」 そのうちに・まもなく
さて、ここに挙げた「そのうちに」と「まもなく」は、厳密に見ると、少し意味が違います。
「まもなく」は「すぐに」に置き換えられますが、「そのうちに」は、「すぐに」よりも「しばらくして」と置き換える方がよい言葉でしょう。
つまり、現代語の「やがて」は、〈ある事柄の直後〉を表す意味と、〈ある事柄のしばらく後〉を表す意味とがあるのです。
これは、古語の「やがて」から引き継いだ意味と、その後、新しく加えられた意味とが混在しているためです。
では、古語の「やがて」はどちらでしょうか。
答えは、〈ある事柄の直後〉を表す言葉、です。
そのような古語の「やがて」について、もう少し詳しく見てみましょう。
2 古語の「やがて」
古語の「やがて」は、〈ある事柄の直後〉を表す言葉で、訳すと次のようになります。
古語の「やがて」 すぐに・そのまま
このうち、「すぐに」の方は、〈ある事柄の直後〉といって納得がゆきやすい訳語ですが、「そのまま」の方は、〈ある事柄の直後〉といわれてもピンとこない、という人もいるかもしれません。
しかし、「そのまま」も、〈ある事柄の直後〉を表しています。
では、このふたつは何が違うのか。それは、「やがて」の前後にある動作や状態が違うのです。
公式風に整理すると、次のようになります。
① A、やがてB →「やがて」は、「すぐに」の意。
② A、やがてA’ →「やがて」は、「そのまま」の意。
①は、「やがて」の前後の動作や状態が、異なったものである場合です。
具体的には、次のような例が該当します。
(例)(鬼ガ)弘徽殿の東欄のほとりに現じて、やがて失せにけり(古今著聞集・593)
(訳)(鬼が)弘徽殿の東の欄干のそばに現れて、すぐに消えてしまった。
「やがて」の前には、「現れる」の意の動詞「現ず」の連用形があり、「やがて」の後には、「消える」の意の動詞「消ゆ」の連用形があります。
「現ず」と「消ゆ」は、ちょうど正反対の動作を表しています。
このような場合の「やがて」は、「すぐに」と訳すのが適切です。
一方、次のような例もあります。
(例)狐その矢に防がれて、倒れて、やがて死ににけり。(古今著聞集・338)
(訳)狐はその矢に行く手を阻まれて、倒れて、そのまま死んでしまった。
「やがて」の前には、「倒れる」の意の動詞「倒る」の連用形「倒れ」があり、「やがて」の後に「死ぬ」の連用形「死に」があります。
「倒る」と「死ぬ」は、動作としては異なりますが、どちらも、〈横たわった状態〉である点は共通します。
このような場合の「やがて」は、「そのまま」と訳すのが適切です。
3 まとめ
それでは、記事をまとめます。
①「やがて」の前後が異なる動作・状態 →すぐに
②「やがて」の前後が類似の状態 →そのまま