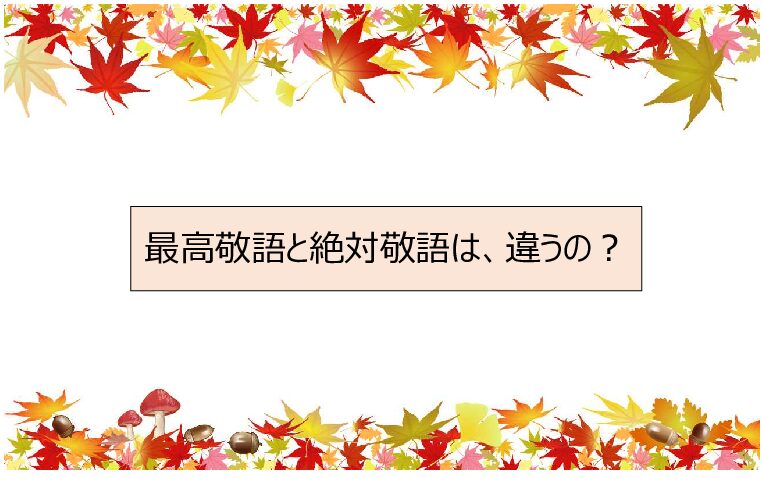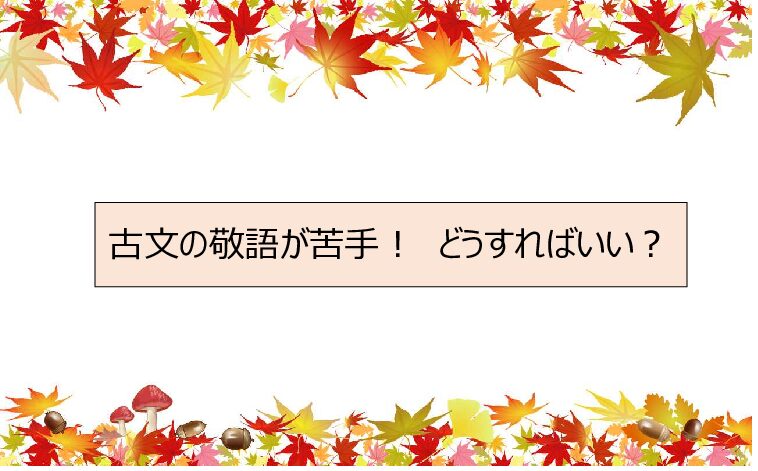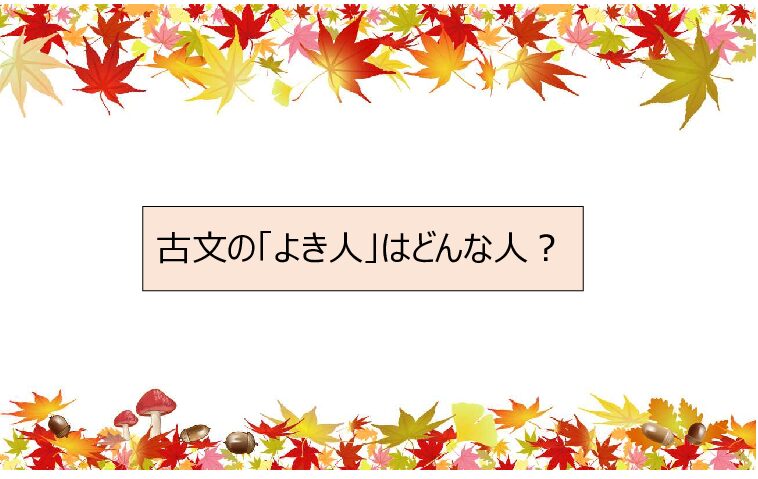注意を要する敬語法の中に、「最高敬語」と「絶対敬語」があります。
どちらも、「最高」とか「絶対」とか、何やら強力な修飾語が付いていて、似た性質を持つような印象を与えます。
しかし、「最高敬語」と「絶対敬語」は、まったく別の敬語法です。
なぜなら、「最高敬語」は尊敬語で、「絶対敬語」は謙譲語だからです。
この記事では、「最高敬語」と「絶対敬語」について説明します。
1 「最高敬語」の種類と働き
まず、「最高敬語」から見ましょう。
「最高敬語」は、先ほど触れたように、尊敬語の表現ですが、特徴は、ふたつの尊敬語を組み合わせて作る、という点にあります。
「最高」と言われると、一種類しかないような感じがしますが、実際には、〈尊敬語+尊敬語〉であれば、すべて「最高敬語」に当たります。
実は、「最高敬語」の別名は「二重尊敬」と言いますが、この名前の方が、〈尊敬語+尊敬語〉であるということが、イメージしやすいかもしれません。
では、具体的な組み合わせを見ましょう。
尊敬語には、動詞、補助動詞、助動詞がありますが、これらの組み合わせによって、次の3種類があります。
①動詞+補助動詞 (例)おはし/たまふ 思しめす
②動詞+助動詞 (例)仰せ/らる
③助動詞+補助動詞 (例)せ/たまふ させ/たまふ しめ/たまふ
動詞の基本原則として、〈動詞+動詞〉という表現はできないため、代わりに、補助動詞や助動詞を組み合わせることになります。
①は、尊敬の動詞に尊敬の補助動詞を加えたもので、「おはしたまふ」は、「あり・をり」「行く・来」などの尊敬語である「おはす」に、尊敬の補助動詞「たまふ」を付けた表現です。
②は、尊敬の動詞に尊敬の助動詞を加えたもので、「仰せらる」は、「言ふ」の尊敬語「仰す」に、尊敬の助動詞「らる」を付けた表現です。
③は、尊敬の助動詞に尊敬の補助動詞を加えたもので、専用の尊敬語を持たない一般の動詞を、最高敬語にするための表現です。
③は、尊敬の助動詞に尊敬の補助動詞を加えたもので、専用の尊敬語を持たない一般の動詞を、最高敬語にするための表現です。
例えば、
(例)[醍醐天皇ガ]宣旨下さしめたまへりしに、(大鏡・左大臣時平)
(訳)[醍醐天皇ガ]宣旨を下しなさったが、
の場合、「下す」という動詞の未然形に、尊敬の助動詞「しむ」の連用形「しめ」、さらに、尊敬の補助動詞「たまふ」の已然形「たまへ」が付いています。
「下す」という動詞には、専用の尊敬語がないため、「下す」に尊敬の助動詞と補助動詞を付けて、「最高敬語」にしています。
なお、①の中の「思しめす」は、尊敬の動詞「思す」に、尊敬の補助動詞「めす」が付いたものですが、補助動詞の「めす」は、ほかに、「聞こしめす」(=「聞く」の最高敬語)、「しろしめす」(=「知る」の最高敬語)などぐらいにしか用いられないため、「思しめす・聞こしめす・しろしめす」を、それぞれ一語の動詞と扱うのが一般的です。
2 「最高敬語」の訳し方
「最高敬語」は、尊敬語を重ねているので、通常の尊敬語よりも、高い敬意を表すことができます。
そのため、特に身分の高い人の動作に使われます。
具体的には、天皇や皇后などの動作に使われますが、天皇や皇后以外にも、大臣などの動作に使われる場合もあります。
いずれにしても、貴族社会の中で、特に身分の高い人が対象となります。
一方で、訳し方には注意が必要です。
古文の敬語は重ねて使うことができますが、現代の敬語は重ねて使うことができません。
そのため、古文の本文で「最高敬語」が使われていても、それをそのまま現代語に置き換えようとすると、現代の敬語の使い方に反してしまいます。
「最高敬語」であっても、訳す際は、通常の尊敬語と同じように訳しましょう。
(例)[帝ハ]源氏の君を限りなきものに思しめしながら、(源氏物語・紅葉賀)
(訳)[帝ハ]源氏の君をこの上ないものとお思いになるものの、
ここでは、最高敬語の「思しめし」が使われていますが、「最高敬語」だからといって、これを「お思いになられる」と訳すのは誤りです。
「お思いになられる」は、「お思いになる」という尊敬表現に、さらに「れる」という尊敬の助動詞を付けた表現ですが、現代の敬語では、このように敬語を重ねるのは誤りとされています。
そのため、ここは「お思いになる」とだけ訳しましょう。
3 「絶対敬語」の種類と働き
次に、「絶対敬語」を見ましょう。
先に見た「最高敬語」がいくつもあるのに対して、「絶対敬語」はふたつしかありません。
たったふたつなので、すぐに覚えてしまいましょう。
絶対敬語 奏す・啓す
「奏す」「啓す」は、どちらも「言ふ」の謙譲語です。
謙譲語は、「動作の受け手」への敬意を表すので、「奏す」「啓す」は、どちらも、「言ふ」という「動作の受け手」、への敬意を表します。
ちなみに、「言ふ」の謙譲語は、ほかに、
「言ふ」の謙譲語:申す・聞こゆ
などがありますが、これらとの違いは、敬意を表す相手が、特定の人物に限られているという点です。つまり、「動作の受け手」が限定されているのです。
動作の受け手
奏す:天皇(上皇・法皇を含む)
啓す:皇后などの天皇の夫人、皇太子などの天皇に次ぐ皇族
申す・聞こゆ:(限定なし)
「奏す」は、「動作の受け手(=言われる人物)」が天皇である場合に用い、「啓す」は、「動作の受け手」が天皇に次ぐ地位の皇族である場合に用いられます。
なお、「奏す」の対象は天皇ですが、天皇経験者(天皇の位を退いた上皇、出家した法皇)も含まれます。
また、訳し方は、
「奏す」の訳し方 申し上げる・奏上する
「啓す」の訳し方 申し上げる
となります。
基本的に、「申す」や「聞こゆ」を訳すのと同じように、「申し上げる」と訳して構いません。
ただし、「奏す」については、「奏」という漢字を利用した、「奏上」という熟語を用い、「奏上する」と訳すことも可能です。
さて、ここまで、絶対敬語の「奏す」「啓す」について説明してきましたが、絶対敬語は、場面の読解に役立つことがあります。
4 「絶対敬語」の読解上のポイント
「絶対敬語」は、使われる相手が限定されていました。
そのため、文章中に「絶対敬語」が使われている場合、その対象となる人物がその場面にいる、ということが分かります。
もし、「奏す」が使われていれば、その場面に「天皇」がいると予想でき、「啓す」が使われていれば、その場面に、皇后か皇太子などがいると予想できます。
実際の例を見ましょう。
(例)中将、人々引き具して、帰り参りて、かぐや姫を、え戦ひとめずなりぬること、こまごまと奏す。(竹取物語) (訳)中将は、人々を引き連れて、帰参して、かぐや姫を、戦って引き留めることができずに終わったことを、こまごまと申し上げる。
これは、『竹取物語』の終わり近くにある一文です。
天人がかぐや姫を迎えに来るということで、天皇は、中将らを派遣して、それを食い止めようとしました。しかし、中将たちは、天人の前では全くの無力で、かぐや姫を引き留めることはできませんでした。
本文の「引き具して」は、「引き連れて」の意で、「え戦ひとめずなりぬる」は、「え~ず」が不可能の意の表現です。
この最後の部分に「こまごまと奏す」とあります。
この箇所には、天皇についての直接的な記述はありませんが、「奏す」という表現が用いられていることから、中将は、天皇に対して、かぐや姫保護が失敗に終わったことを報告をしている場面だと分かるのです。
このように、「絶対敬語」は、場面理解に活用できるので、しっかりと覚えておきましょう。
5 まとめ
記事をまとめます。
① 「最高敬語」は、尊敬語+尊敬語でできた敬語で、特に身分の高い人の動作に用いられる。
② 「絶対敬語」は「奏す・啓す」の2語のみで、どちらも「言ふ」の謙譲語である。
③ 「絶対敬語」の「奏す」は、相手が天皇の場合にのみ用い、「啓す」は、相手が皇后・皇太子などの場合にのみ用いる。