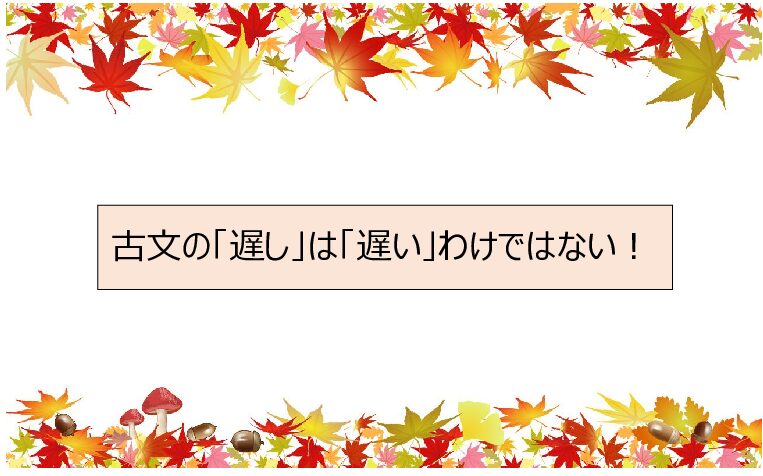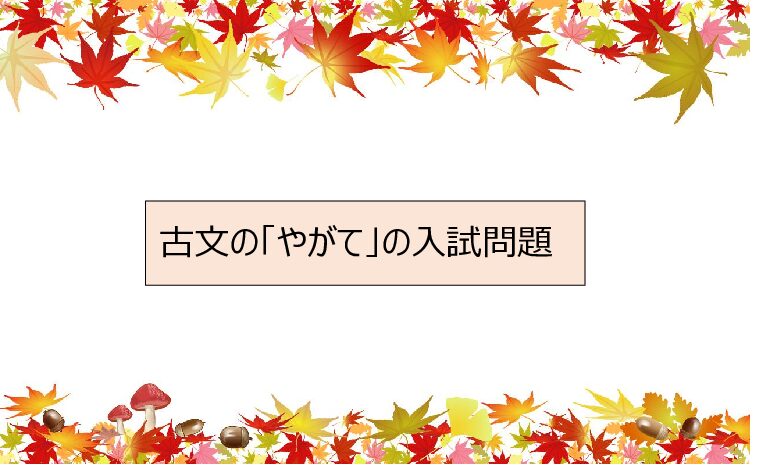古文を読む際に注意が必要な言葉のひとつは、現代語と古語で意味の違う言葉です。
現代語にもある言葉だと、つい、現代語と同じ意味だと思ってしまい、それで文脈を取り違えてしまうこともあります。
今回紹介するのは、「遅し」という言葉です。
「遅し」は、現代語の「遅い」のもとになった形容詞ですが、現代語の「遅い」とはニュアンスが異なります。
具体的には、「遅く○○」(○○は動詞)は、「遅く○○する」という意味ではなく、「なかなか○○しない」という意味を表します。
しかも、この意味は、古語辞典によっては載せていないものもあるため、注意が必要です。
1 古語辞典の説明
まず、古語辞典の説明を紹介します。
「遅し」について、詳しく説明しているのは、『旺文社古語辞典 第十版』です。
語義の説明として、
①【遅し】遅い。時刻におくれている。なかなか…しない。
と挙げ、さらに【学習】の項で、
古語の「おそし」
事態の進行に思ったよりも時間がかかるというのが現代語の意味である。古語では、ある基準となる時点で、まだ、そうなっていないという意味で使われる。(以下略)
と説明しています。
これを念頭に置きつつ、いくつかの古語辞典で、「おそし」を引いてみると、
大修館書店『新全訳古語辞典』 ①【遅し】遅い。のろい。
『三省堂 全訳読解古語辞典 第五版』 一【遅し】遅れている。おそい。
『旺文社全訳古語辞典 第五版』 ①【遅し】(時期に)遅れている。遅い。なかなか…しない。
『学研全訳用例古語辞典 改訂第二版』 ②〔「おそく+動詞」の形で〕なかなか…しない。
となっていました。
『旺文社全訳古語辞典 第五版』は、「なかなか…しない」の意を載せ、『学研全訳用例古語辞典 改訂第二版』は、〔「おそく+動詞」の形で〕と条件を付けたうえで、「なかなか…しない」の意を載せていました。
一方、大修館書店『新全訳古語辞典』と『三省堂 全訳読解古語辞典 第五版』は、語義説明の中に、「なかなか…しない」の意は載せていませんでした。
「なかなか……しない」という意味を載せていない辞書があるということは、そもそも、間違った意味なのではないかと思う人もいるかもしれません。
そこで、実際の古文で確認してみましょう。
2 『古本説話集』の例
『旺文社古語辞典 第十版』では、先ほどの引用箇所の後に、『蜻蛉日記』の例を紹介しています。
興味のある方は、実際に、『旺文社古語辞典 第十版』を見ていただくことにして、ここでは、別の例を紹介したいと思います。
それは、『古本説話集』の例です。
(例)その日になりて、人々歌ども持て参りたりけるに、大納言、遅く参りければ、御使して、遅きよしをたびたび仰せられ、つかはす。(『古本説話集』・第二)
(訳)その日になって、人々が歌々を持って参上したが、大納言は、なかなか参上しなかったので、(道長ハ)御使者に命じて、遅い旨を何度もおっしゃり、派遣する。
これは、藤原彰子が入内(=宮中に入ること)するに当たって、父である藤原道長が、調度品として屏風を作らせ、その屏風に貼り付ける歌を人々に詠ませた時の話です。
「大納言」は、才人として知られた藤原公任のことで、「その日」とは、和歌を屏風に貼り付ける当日のことです。
「参りければ」は、「来」の謙譲語「参る」の連用形に、過去の助動詞「けり」の已然形、原因・理由の接続助詞「ば」が付いたもので、「参上したので」の意を表します。
後半の「御使して、遅きよしをたびたび仰せられ、つかはす」の部分の主語は、藤原道長で、その道長が、「御使」に命じて、「遅きよし(=遅い旨)」を「たびたび仰せられ(=何度もおしゃっ)」た、とあります。
この場合、「遅く参りければ」を、「(大納言が)遅く参上したので」と訳すと、その後で、道長が何度も「遅い遅い」と、催促の使者を送ったことの意味が分からなくなります。
ここは、大納言がなかなか来ないので、道長が催促の使者をやると見るのが適切です。
つまり、「大納言、遅く参りければ」は、「大納言が、なかなか参上しなかったので」と訳す必要があり、この「遅く」は、明らかに、「なかなか…しない」の意と見られるのです。
このように、実際の古文作品を見ても、「遅く○○」が「なかなか○○しない」の意であることが分かります。
3 まとめ
それでは記事をまとめます。
古語の「遅く○○」は、「遅く○○する」の意ではなく、「なかなか○○しない」の意を表す。