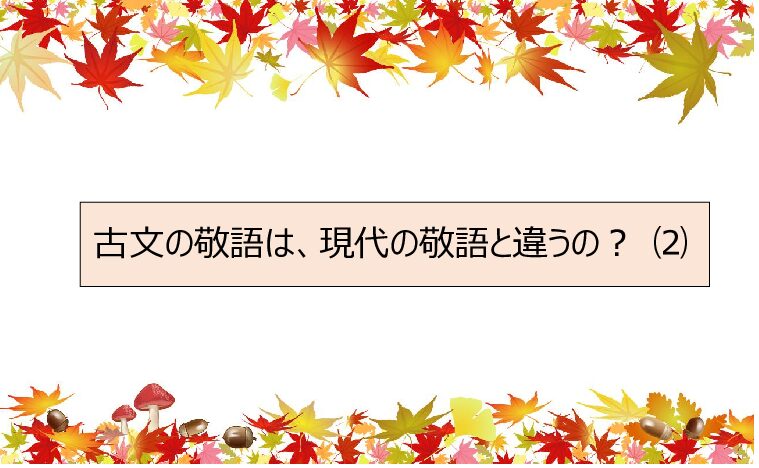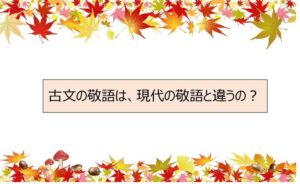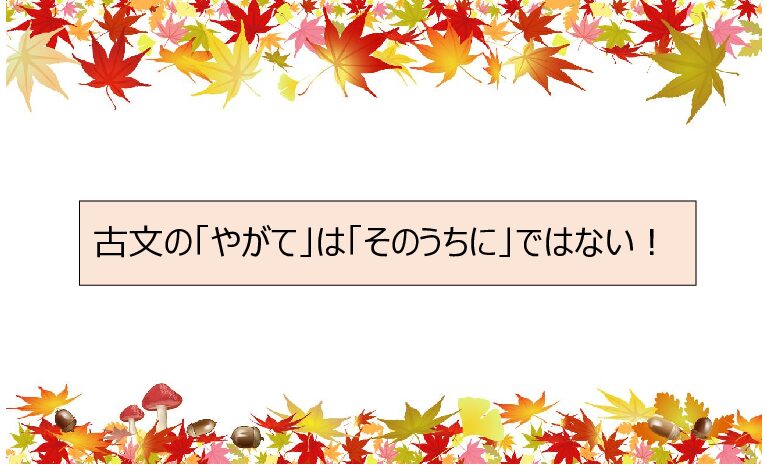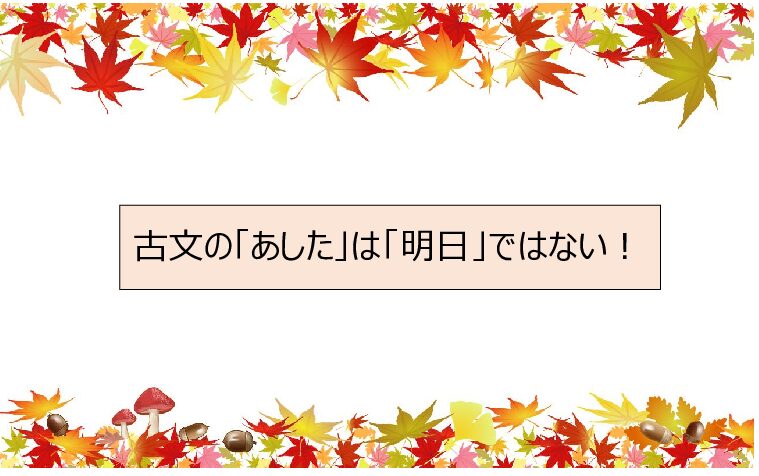以前の記事で、古文の尊敬語、丁寧語は、現代の尊敬語、丁寧語と同じであることを説明しました。
今回は、残りの謙譲語について説明します。
1 謙譲語の場合
謙譲語だけ、別の記事にしたのは、古文の謙譲語と現代の謙譲語には、違いがあるためです。
違いの説明をする前に、まずは、共通点を見ておきましょう。
現代の謙譲語と古文の謙譲語の定義を並べると、次のようになります。
現代の謙譲語:話し手が、自分の動作や状態などをへりくだって言うことで、相手への敬意を表す。
古文の謙譲語:話し手が、話題の中の動作の受け手への敬意を表す。
古文の謙譲語は、敬意の対象が「動作の受け手」と説明されています。
一方、現代の謙譲語は、「相手への敬意」という説明をしていますが、この「相手」というのは、「自分の動作」が及ぶ「相手」のことで、それを言い換えると、「動作の受け手」となります。
ちなみに、「自分」は、〈動作をする人物〉なので、ここでは、「自分」が「動作主」に当たります。
そのため、「自分の動作や状態をへりくだって言う」というのは、「動作主を低める」ということになり、現代の謙譲語は、「動作主を低めて、動作の受け手への敬意を表す」と言い換えることができます。
話が少しそれましたが、現代の謙譲語も、古文の謙譲語も、「動作の受け手」への敬意を表しているという点では共通しています。
では、どこに違いがあるのでしょうか。
それは、現代の謙譲語の定義に出てくる、「自分の動作や状態などをへりくだって言うことで」という部分です。
なぜなら、古文の謙譲語については、〈動作主を低める〉という言い方が不適当だと考えられているからです。
2 古文の謙譲語は、動作主を低めない
古典文学の研究者によく参照されている文法辞典に、小田勝『実例読解 古典文法奏覧』(和泉書院)という本があります。
この本の中には、次のような説明があります。
補語尊敬語は、主語を低める働きはなく、単に補語に対する敬意を表すと考えなければならない。(551ページ)
聞き慣れない専門用語が出てきますが、ここでいう「補語尊敬語」とは「謙譲語」のことで、「主語」とは「動作主」、「補語」とは「動作の受け手」を指しています。
それを踏まえて、分かりやすく言い直すと、
謙譲語は、動作主を低める働きはなく、単に動作の受け手に対する敬意を表すと考えなければならない。
となります。
つまり、古文の謙譲語には、〈動作主を低める〉という働きはないというのです。
なぜ、そのように考えられるのでしょうか。
『実例読解 古典文法奏覧』では、次のような例文を挙げて説明しています。
[帝ハ]一の宮を見奉らせ給ふにも(源氏物語・桐壺)
これは、『源氏物語』の「桐壺」巻の一節で、「桐壺の帝」が、「第一皇子(=一の宮)」の様子を見ながら、亡くなった「桐壺の更衣」の私邸に下がっている「第二皇子(=光源氏)」のことを思う、という場面の一部です。
ここでは、帝の動作が「見奉らせ給ふ」と表現されています。このうち、「奉らせ」が謙譲語で、この「奉らせ」の敬意の対象は、「見る」という動作の受け手である「一の宮」です。
一方で、身分の上下に注目すると、「帝」は世の中で最も身分の高い人物であり、当然、「一の宮」よりも高い身分です。その最高位の人物である「帝」の動作に謙譲語が用いられている点がポイントです。
もし「謙譲語」に「動作主を低める働き」があるならば、この場面の話し手は、わざわざ、最も身分の高い「帝」を低めて、(帝よりも身分の低い)「一の宮」に敬意を示したことになってしまいます。
これは、不自然な現象ですね。
このような不自然さを解消するためには、古文の謙譲語に、動作主を低めるという働きはなく、ただ、動作の受け手への敬意を示しているだけである、というように考え方を変える必要があります。
以上のような背景があり、古文の謙譲語については、〈動作主を低める〉という説明は適合しません。したがって、この点が、現代の謙譲語と古文の謙譲語の違いといえるでしょう。
皆さんも、古文の謙譲語は、「動作の受け手への敬意を表す」という特徴のみを覚えておくようにしましょう。
3 まとめ
記事をまとめます。
古文の謙譲語には、〈動作主を低める〉という働きがなく、その点で、現代の謙譲語と異なっている。