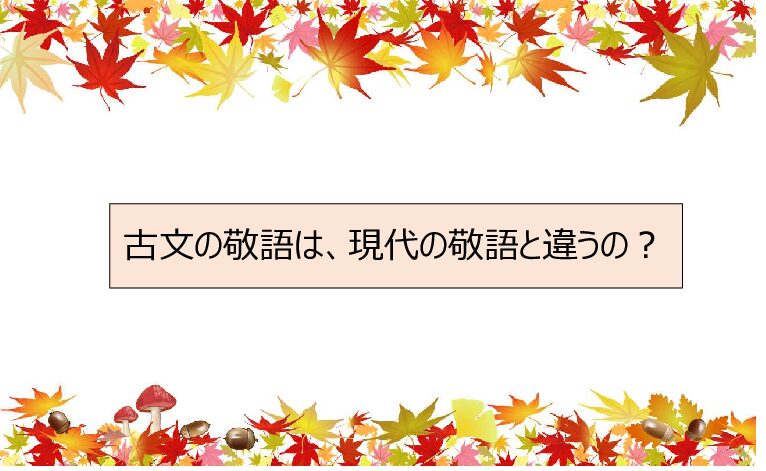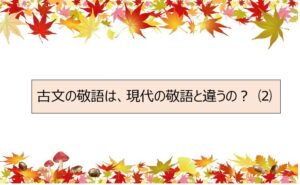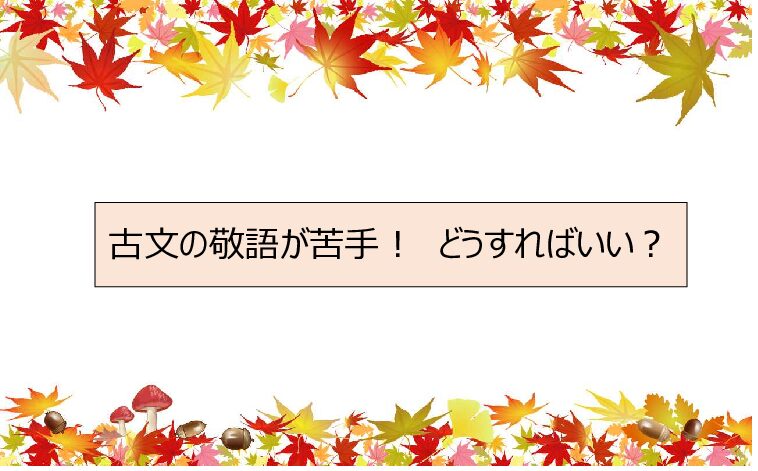古文の敬語を学習した人が、最初に気になるのは、古文の敬語は、現代の敬語と同じなのか、違うのか、という点でしょう。
結論から言うと、古文の敬語と現代の敬語は、基本的に同じです。
ただ、「基本的に」なので、一部に違いもあります。
この記事では、古文の敬語と現代の敬語の共通点、相違点について、主に尊敬語と丁寧語を取り上げて説明します。
なお、謙譲語については、別の記事をご覧ください。
1 現代の敬語と古文の敬語の定義
現代の敬語については、だいたい中学校で学習しますが、およそ、次のように習うと思います。
尊敬語:話し手が、相手の動作や状態などを高めて言うことで、相手への敬意を表す。
謙譲語:話し手が、自分の動作や状態などをへりくだって言うことで、相手への敬意を表す。
丁寧語:話し手が、丁寧な表現を用いることで、話の聞き手への敬意を表す。
一方、高校で習う古文の敬語では、次のように説明されていることが多いでしょう。
尊敬語:話し手が、話題の中の動作主への敬意を表す。
謙譲語:話し手が、話題の中の動作の受け手への敬意を表す。
丁寧語:話し手が、話の聞き手への敬意を表す。
全体を見渡して、まず、「話し手」が敬意を表している、とする点は、すべての敬語に共通しています。
この点を踏まえた上で、さらに、それぞれを見比べてみましょう。
2 尊敬語の場合
まずは、尊敬語です。
現代の尊敬語と古文の尊敬語の定義を並べてみると、
現代の尊敬語:話し手が、相手の動作や状態などを高めて言うことで、相手への敬意を表す。
古文の尊敬語:話し手が、話題の中の動作主への敬意を表す。
となります。
先ほど見たように、「話し手」が敬意を表すという点は、共通しています。
では、誰に対して敬意を表しているのでしょうか。
古文の尊敬語では、「動作主への敬意を表す」とあります。
一方、現代の尊敬語では、「相手への敬意を表す」とあり、古文の場合と少し説明が異なっています。
けれども、この「相手」というのは、「動作や状態など」の主語に当たる人物、つまり「動作主(=動作をする人)」を指しており、現代の尊敬語も、やはり「動作主」への敬意を示していることになります。
以上のことから、現代の尊敬語と古文の尊敬語は、どちらも、「話し手」から、「動作主」への敬意を表すものとして、同じであることが分かります。
現代の尊敬語には、「相手の動作や状態などを高めて言うことで」という説明がありますが、これは、敬意の表し方の具体的な方法を説明しているもので、敬意の対象が、古文の尊敬語と違っているわけではありません。
3 丁寧語の場合
次に、謙譲語を一旦飛ばして、丁寧語について見ます。
現代の丁寧語と古文の丁寧語の定義を並べると、
現代の丁寧語:話し手が、丁寧な表現を用いることで、話の聞き手への敬意を表す。
古文の丁寧語:話し手が、話の聞き手への敬意を表す。
となります。
現代の丁寧語は、「丁寧な表現を用いることで」という、具体的な敬意の表し方を説明していますが、それ以外は、古文の丁寧語の説明とまったく同じです。
つまり、どちらの丁寧語も、「話し手」が、「話の聞き手」に敬意を表している、ということになり、現代の丁寧語と古文の丁寧語は、やはり同じものと考えてよいでしょう。
4 まとめ
ここまでの記事をまとめます。
①古文の尊敬語は、現代の尊敬語と、基本的に同じものである。
②古文の丁寧語は、現代の丁寧語と、基本的に同じものである。