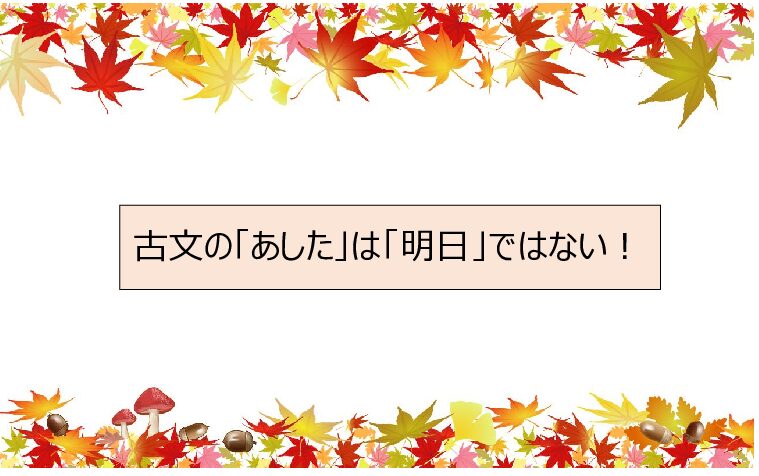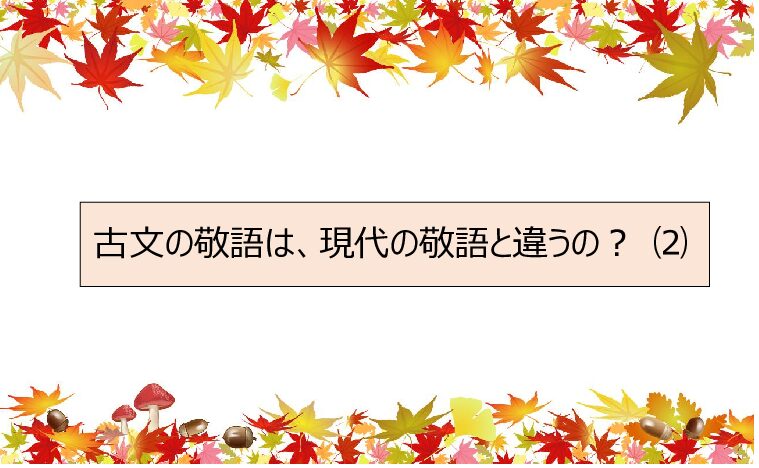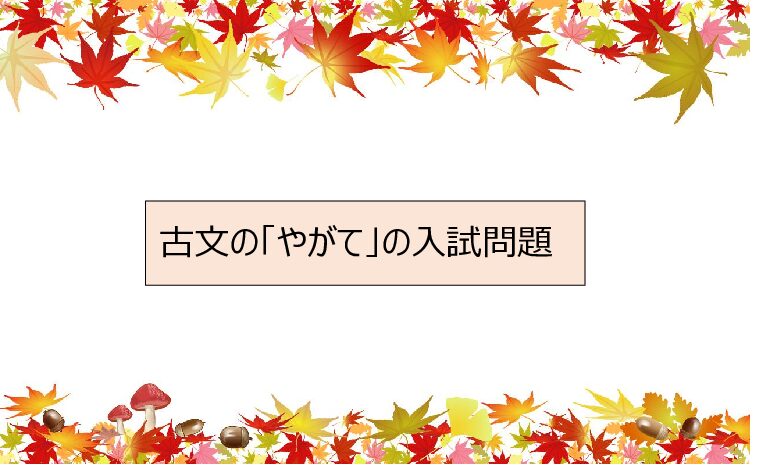古文を読む際に注意が必要なのは、現代語と古語で意味の違う言葉です。
現代語にもある言葉だと、つい、現代語と同じ意味だと思ってしまい、それで文脈を取り違えてしまうこともあります。
今回紹介するのは、「あした」です。
1 現代語の「あした」
まず、現代語の「あした」の意味を確認しましょう。
例えば、『明鏡国語辞典 第三版』で「あした」を引くと、
今日の次の日。あす。明日。
とあります。
ここでは、「あした」の意味に、「あす」が含まれています。
また、「あした」と「あす」の違いについては、「使い方」の項に、
(「あした」の)改まった言い方に「あす」、さらに改まった言い方に「明日」がある。
という説明があり、「あす」は「あした」の「改まった言い方」とされています。
確かに、普段の生活では、「あした」を使い、「あす」を使うケースは少ないと思われます。
つまり、現代語では、「あした」と「あす」は、同じもの(=「今日の次の日」)を指し、違いは、普段使いの言葉か、改まった言葉か、という点にあるだけです。
ところが、古語では、「あした」と「あす」は別のものを指す、別の言葉です。
2 古語の「あした」
古語の「あした」は、「あす」ではなく、「あさ」の意を表します。
例えば、
(例)ゆふへ置きてあしたは消ぬる白露の消ぬべき恋も我れはするかも(万葉集・3039)
(訳)夕方に置いて朝には消えてしまう白露のように、(身も)消えそうな恋も私はすることだなあ。
この歌では、「あした」は、「夕方」の意の「ゆふへ」と対になっていて、「朝」の意を表していることがよく分かります。
ちなみに、古語の「あす」は、
(例)あすよりは春菜摘まむと標めし野に昨日も今日も雪は降りつつ(万葉集・1427)
(訳)明日からは春菜を摘もうと標縄を張っておいた野に、昨日も今日も雪は降り続いていて。
のように、「昨日」や「今日」と対比的に使われた例があり、「明日」の意であることが分かります。
3 まとめ
記事をまとめます。
①現代語では、「あす」と同じ。
②古語では、「あさ」の意。